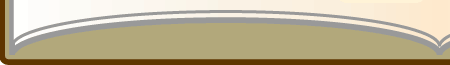| ● ベカ舟の構造(こうぞう) |
|
(1)特徴(とくちょう)
カジキとウワダナの接合部分(せつごうぶぶん)に「ノッケ作り」という技法(ぎほう)が使われています。普通(ふつう)の船は「ワキズケ」という技法(ぎほう)が使われていますが、ベカ舟の場合、海苔柵(のりさく)の間に入って作業をするため、「ワキヅケ」では海苔ヒビの枝(えだ)にひっかかってしまいます。そのため、カジキの上にウワダナをのせる「ノッケ」という技法が使われていました。 |
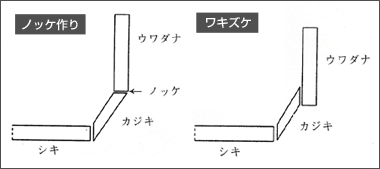 |
|
|
(2)海苔(のり)とり専用(せんよう)のベカ舟
|
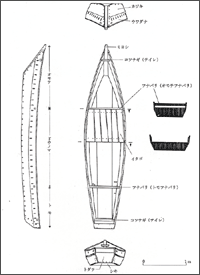 |
「ノリベカ」と呼(よ)ばれるベカ舟は、長さ15尺(しゃく)〔約(やく)4.8メートル〕、幅(はば)3尺〔約95センチ〕、船体は7〜8分〔約2.1〜2.4センチ〕の杉板で作られています。
※1間=約(やく)1.8メートル、
1尺=約30センチメートル、
1寸=約3センチメートル、
1分(ぶ)=約3ミリメートル
|
 |
|
|
|
(3)腰(こし)タブ漁(りょう)に使われるベカ舟
|
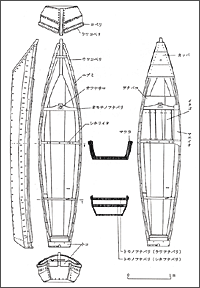 |
長さ16尺(しゃく)〔約(やく)4.8メートル〕、幅(はば)3尺1寸(すん)5分(ぶ)〔約95センチ〕、船体は7〜8分〔約2.1〜2.4センチ〕の杉板で作られています。この船には、「コベリ」「ウワコベリ」といった船体を守る部分がついていて、腰タブ漁のときには、このベカ舟に一斗樽(いっとだる)で20〜30杯(ぱい)もの貝を運(はこ)んでいました。
※1斗(と)=約1.8リットル |
 |
|
|
| |