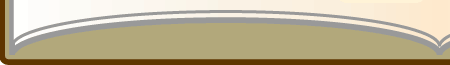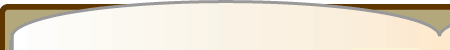 |
 |
 |
 |
|
| ● 貝の天敵(てんてき) |
| |
| ●ホトトギスガイ |
 |
 |
 |
| |
▲ドッタリ |
|
|
| |
大きさ2cmくらいの二枚貝です。足糸(そくし)を出して、アサリなどの漁場(ぎょじょう)の砂の上に集団でかたまりを作って生息(せいそく)します。
アサリなどの下にホトトギスガイの集団がいると、アサリはえさをとることや、呼吸(こきゅう)をすることができなくなり死んでしまいます。
漁師(りょうし)はそれを防(ふせ)ぐために「ドッタリマンガ」とよばれる1mほどのフォークでホトトギスガイの集団をほりおこし、バラバラにしてアサリを救(すく)いました。 |
 |
 |
| ▲ドッタリマンガ |
|
|
| |
| ●ヒトデ |
 |
|
| |
ヒトデは腹(はら)がわにたくさんある管足(かんそく)という部分で貝ガラを開き、貝の中に毒(どく)のようなものを出して貝をマヒさせて食べてしまいます。
昭和(しょうわ)28年(1953)10月ごろから、東京湾の各地でヒトデが大発生し、貝漁(かいりょう)は大きな被害(ひがい)を受けました。『浦安町誌(うらやすちょうし)(上)』には、「貝の養殖場(ようしょくじょう)はさながら黄色いじゅうたんをしきつめたようにヒトデでうまった。」ということが書かれています。その被害は当時のお金で1億150万円といわれています。 |
|
|
|