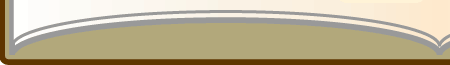| ● キティ台風で高潮(たかしお)が発生した要因(よういん) |
| |
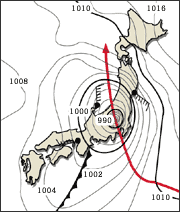 |
 |
▲昭和24年(1949)8月31日午後9時の天気図
『東京湾(とうきょうわん)の汚染(おせん)と被害(ひがい)』より
※気圧の単位はhp(ヘクトパスカル) |
 |
|
|
 |
キティ台風は、昭和(しょうわ)24年(1949)8月27日、マーカス島東南で発生し、時速(じそく)20kmの速度(そくど)で北上しました。31日午後8時すぎに茅ヶ崎(ちがさき)付近(ふきん)に上陸(じょうりく)し、その後熊谷(くまがや)、新潟(にいがた)を通過(つうか)して日本海へと抜(ぬ)けていきました。最(もっと)も東京に近づいたのが午後8時30分で、平均風速(へいきんふうそく)25m、最大瞬間風速(さいだいしゅんかんふうそく)31m、最低気圧(さいていきあつ)は986ヘクトパスカルでした。 |
|
| |
| ・高潮が発生した3つの要因(よういん) |
| |
| 【台風の進路(しんろ)と風向き】 |
 |
 |
台風は、中心の回りを左回りに回っていきます。浦安などの海岸近くでは南東の強い風が海から吹(ふ)いてくることになり、この吹き寄(よ)せ作用で湾(わん)の奥部(おくぶ)では激(はげ)しく水位(すいい)が高まりました。
漁師(りょうし)たちの間では、風向きの変化(へんか)について、「イナサ〔南東〕の風が吹くと、堤防が危(あぶ)ない」「ミナミ[南]の風になると、もう大丈夫(だいじょうぶ)だ」と、経験(けいけん)から語り伝(つた)えられているものがあります。 |
|
|
| |
| 【気圧(きあつ)の吸(す)い上げ作用】 |
 |
 |
台風の中心は、周辺(しゅうへん)に比(くら)べると激(はげ)しく気圧(きあつ)が下がります。そのため、気圧の吸い上げ作用で、周辺の海面は大きくふくれあがり、水位が上昇(じょうしょう)しました。吸い上げられる量は、気圧が1ヘクトパスカル下がると、海面はほぼ1センチメートル上昇するという関係(かんけい)にあります。 |
|
|
| |
| 【満潮(まんちょう)】 |
 |
 |
台風の通過時刻(つうかじこく)と満潮時(まんちょうじ:午後9時30分)がちょうど重なったため、雨による河川(かせん)の増水(ぞうすい)と、満潮(まんちょう)による海水の流れの逆流(ぎゃくりゅう)により、浦安の近くの海一帯(いったい)は、いちじるしく潮位(ちょうい)が上昇し、高潮となって堤防(ていぼう)を決壊(けっかい)させ、南砂町(みなみすなまち)、葛西(かさい)、浦安などの地域(ちいき)に大きな被害(ひがい)をもたらしました。 |
|
|
| |