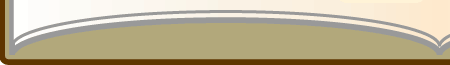| 年月日 |
できごと |
| 昭和(しょうわ)
32年(1957) |
| 10月 |
| ● |
「ドラムバーカー」の設置許可(せっちきょか)を受ける。
|
|
|
| ◎ |
東京都の指示(しじ)
「ドラムバーカー設置を許可するにあたり、直接廃液(はいえき)を江戸川に放流(ほうりゅう)せず、廃液をためる池を作るべきである。」 |
|
昭和(しょうわ)
33年(1958)
|
| 4月7日 |
| ○ |
江戸川の水がどす黒くにごり、魚介類(ぎょかいるい)が死んでいた。漁業協同組合(ぎょぎょうきょうどうくみあい)が調(しら)べたところ、本州製紙江戸川工場(ほんしゅうせいしえどがわこうじょう)からよごれた水が流れ出していることがわかった。 |
|
| 5月17日 |
○
● |
漁業協同組合側と工場側で合同調査(ごうどうちょうさ)をして、被害(ひがい)の様子(ようす)を確認(かくにん)する。 |
|
| 5月23日 |
| ○ |
浦安の漁業組合の他に、6つの漁業組合がよごれた水を放流しないように、工場側に訴(うった)えた。
|
|
|
| ● |
漁業組合の願(ねが)いを聞かず、よごれた水を放流し続ける。 |
|
| 5月24日 |
| ○ |
7つの漁業組合員約(やく)300名が工場に集まる。まだよごれた水が放流されていることを知り、工場のガラスを割(わ)ったりきたない水を止めたりする。
|
|
|
| ● |
漁師たちの暴行(ぼうこう)を非難(ひなん)する。また、「いつか被害を受けた漁師たちに補償(ほしょう)をするので、工場内の機械(きかい)の運転(うんてん)を続けさせてほしい」と主張する。
|
|
|
| ◎ |
5月24、28、29日の3日間、おたがいに交渉(こうしょう)しあったものの、決着(けっちゃく)がつかずに終わった。 |
|
| 5月30日 |
| ○ |
漁業組合の代表者(だいひょうしゃ)が千葉県庁(ちばけんちょう)に訴(うった)えに行く。 |
|
| 6月6日 |
| ○ |
東京都の漁業組合の代表が、よごれた水の放流をすぐにやめさせるように、東京都庁(とうきょうとちょう)に訴(うった)える。 |
|
|
| ◎ |
東京都庁は「すぐによごれた水の放流をやめ、漁師たちと話しあいなさい」と工場側に伝える。 |
|
| 6月9日 |
| ● |
「排水を中止して、話し合いがつくまでは工場の運転はしない」と約束(やくそく)するが、「工場の運転を再開(さいかい)する」と一方的に浦安町議会(うらやすちょうぎかい)に連絡を入れる。 |
|
| 6月10日 |
| ○ |
午前11時から、浦安小学校付属幼稚園(ふぞくようちえん)で、約2,000人が参加(さんか)する町民大会(ちょうみんたいかい)が開催(かいさい)される。 |
|
|
| ○ |
その後、約800人が国会(こっかい)と都庁に訴えに行く。
|
|
|
| ● |
鉄門をしめ、漁師たちを中に入れないようにする。 |
|
|
| ○ |
国会・都庁に訴えに行った後、午後6時ごろ漁師たちが工場に到着する。鉄門を押(お)し破(やぶ)り工場内に入り、乱闘事件(らんとうじけん)に発展(はってん)する。 |
|
|
| ◎ |
逮捕者(たいほしゃ)8名、重軽傷者(じゅうけいしょうしゃ)105名の大事件になる。 |
|
|
| ◎ |
小松川警察署員(こまつがわけいさつしょいん)と第二機動隊員(きどうたいいん)が漁師たちを押さえるために出動(しゅつどう)する。警察官の数600名、警察官の重軽傷者38名 |
|
| 6月11日 |
| ○ |
町のいたる所に「よごれた水の放流をすぐに中止しろ。我われを死においやる本州製紙をぶっつぶせ。」というポスターがはられる。 |
|
|
| ◎ |
浦安町議会はこの事件の負傷者(ふしょうしゃ)の治療費(ちりょうひ)を町が負担(ふたん)することを決める。 |
|
昭和(しょうわ)
33年(1958)
|
| 12月25日 |
| ◎ |
国会において、「公共用水域(こうきょうようすいいき)の水質(すいしつ)の保全(ほぜん)に関する法律(ほうりつ)」が制定される。 |
|