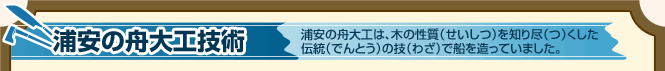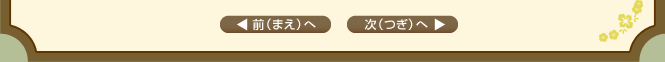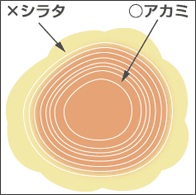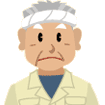|
|
| ●船造(ふなづく)りが盛(さか)んな浦安 |
 |
| 昭和(しょうわ)17年(1942)頃(ごろ)、浦安では当代島(とうだいじま)に1軒(けん)、猫実(ねこざね)に3軒、堀江(ほりえ)には舟大工が2軒ありました。浦安の木造船(もくぞうせん)は「仮屋(かりや)」と呼(よ)ばれる小屋で造られ、さまざまな船の製造(せいぞう)・修理(しゅうり)が行われていました。 |

|
| ●船の材料(ざいりょう)の確保(かくほ)・準備 |
 |
|
 |
| 舟大工の仕事はよい材料を確保することからはじまります。それは漁師(りょうし)が船を発注(はっちゅう)するとき、材料をみてから決めるからです。船を作る際、スギ・カヤ・ヒノキ・ケヤキ・マツ・カシ・シオジなどの木材を使用しました。特にスギは船体(せんたい)のおもな部分であるシキ(底板)・カジキ(側板下部)・ウワダナ(側板上部)などに使われます。 |
 |
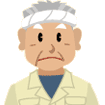 |
 |
 |
 |
 |
江戸川河口域(えどがわかこういき)は淡水(たんすい)と海水が混じった汽水域(きすいいき)だから、シラタを使った船は3年もすると腐(くさ)っちまうんだ。でも浦安の船はスギのアカミだけをぜいたくに使ってあるから長持ちするんだぞ。 |
 |
 |
 |
 |
|
|

|
| ●船の製造の前に決めること |
 |
| 舟大工(ふなだいく)は、漁師(りょうし)から注文(ちゅうもん)を受けた船の種類(しゅるい)によって、大工さんの人数や制作日数(せいさくにっすう)を決めていきます。 |
 |
| 船 |
制作日数
(せいさくにっすう) |
延(の)べ人数 |
| 打瀬船(うたせぶね) |
約2ヶ月 |
60〜70人 |
| マキ船 |
約2ヶ月 |
60〜70人 |
| 投網船(とあみぶね) |
約2ヶ月 |
60〜70人 |
| 小網船(こあみぶね) |
約1ヶ月 |
30〜40人 |
| ベカ舟 |
約1週間 |
7人 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
舟大工の修行(しゅぎょう)は、誰も技術は教えてくれないんだ。だから盗(ぬす)んで覚(おぼ)えたんだ。大変だったな〜。
ベカ舟ぐらいだったら図面(ずめん)なしで一週間(いっしゅうかん)ぐらいで造れるぞ。 |
 |
 |
 |
 |
|
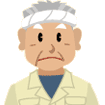 |
|

|
| ●船の値段(ねだん) |
 |
| 船は値段(ねだん)が高いので、みんなで集まってお金を出し合い、お金をためていました。その集まりを船無尽(ふねむじん)といいます。このお金をみんなで順番に使い、新造船(しんぞうせん)を作りました。 |
 |
| 【昭和(しょうわ)30年頃の船の値段】 |
 |
船
(材料・大きさによってかわります) |
値段 |
| 打瀬船(うたせぶね) |
18〜22万円 |
| マキ船 |
16〜22万円 |
| 投網船(とあみぶね) |
20〜22万円 |
| 小網船(こあみぶね) |
およそ10万円 |
| ベカ舟 |
およそ2万円 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
この頃(ころ)の1万円の価値(かち)は、今(2006年)の6万円ぐらいするんだ。
船がどんなに高いか分かるかな? |
 |
 |
 |
 |
|
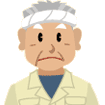 |
|
|
 |