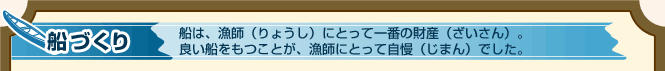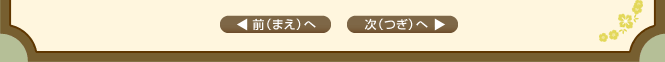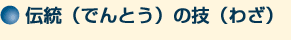 |
 |
| 浦安の舟大工(ふなだいく)たちは、木の性質(せいしつ)を知り尽(つ)くしていました。そんな舟大工たちの船づくりの伝統(でんとう)や技術、道具を見てみよう。 |
| |
| ● すり合わせ |
 |
|
|

|
「すり合わせ」という舟大工ならではの防水技術(ぼうすいぎじゅつ)は、3本ののこぎりを使って行いました。
木を切るためにのこぎりを引くのではなく、木と木の接合面(せつごうめん)をすり合わせるためにのこぎりを使ったのです。
最初(さいしょ)に「中目(ちゅうめ)」と呼ばれるのこぎりを使い、次に「こば」か「13目」。最後(さいご)は「16目」というのこぎりで仕上げました。のこぎりの目は使う順に細くなっています。 |
|
| |
| ● 木殺(きごろ)
し |
 |
|

|
すり合わせが終わると、その断面(だんめん)を叩(たた)いて「木殺し」をします。舟が水につかると、木殺しをした部分(ぶぶん)がふくらみ、板と板がくっつき、水がもれなくなります。 |
|
| |
| ● 角度(かくど)のある板の釘(くぎ)打ち |
 |
|

|
角度をつけてつなぎたい二枚の板がある場合、板に打ち込む前に、釘(くぎ)を叩(たた)いて、板と同じ角度をつけます。
こうすることで、釘を打ち込みやすくなり、また釘がはずれにくくなります。 |
|
| |
| ● のこぎりの修理方法(しゅうりほうほう) |
 |
のこぎりには、縦(たて)びきと横びきの2種類(しゅるい)があります。これらは刃(は)の向きがちがい、それぞれの刃の角度(かくど)にそって、とがらせていきます。これを「目だて」といいます。
使っては修理(しゅうり)ということをくり返し、舟大工たちは道具の形が小さく変(か)わってしまうまで、大切に使っていました。さらに自分が使いやすいように、のこぎりの柄(え)の部分も改造(かいぞう)しました。 |
| |
|
| ▲ 修理をくりかえすことで、小さくなっていったのこぎり |
| |