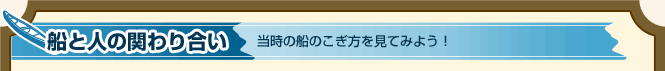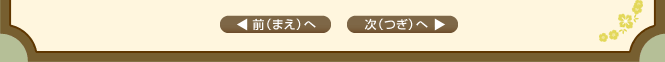|
| ● 浦安の船こぎ名人 |
 |
 |
 |
 |
 |
「櫂(けえ)は三年、櫓(ろ)は三月」なんていわれるくれぇ、船をあやつるのはむずかしいんだ。 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
 |
| 【浦安の船こぎ名人】 |
 |
| 浦安では |
| ● |
櫂(けえ)の名人は、洒落櫂(シャレゲエ)という技 を使う「鵜縄漁師(うなわりょうし)」 |
| ● |
櫓(ろ)の名人は、「延縄漁師(はえなわりょうし)」 |
| ● |
櫂(けえ)と櫓(ろ)を使い分け、自在に船を操(あやつ)る名人は、「投網(とあみ)のカジコ」 |
|
| と言われていたんだよ。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
| |
| ● 櫂(かい) |
 |
 |
 |
 |
 |
浦安では櫂(かい)のことを「ケエ」って
呼んでたんだ。 |
 |
 |
 |
 |
|

|
|
| |
| |
 |
浦安で使われていた櫂(かい)にはいろいろな種類がありました。その長さから、それぞれ「二尋(ふたひろ)ヤブキ」「三尋(みひろ)ヤブキ」「四尋(よひろ)ヤブキ」などと呼ばれていました。また、短い櫂を「ツイゲ(ツイネ)」、長い櫂を「オオヤブキ」を呼(よ)んでいました。
船を進ませるには、櫂で海底を突(つ)きました。深い場所では櫂を櫓(ろ)のように使っていました。これを櫂櫓(ケエロ)と呼んでいました。 |
|
| |
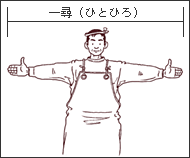 |
 |
| ▲一尋(ひとひろ)は大人の男性が腕(うで)を広げた長さで、約(やく)1.8メートルです。 |
|
|
 |
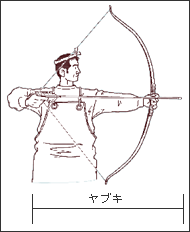 |
 |
| ▲二尋(ふたひろ)ヤブキは二尋(約3.6メートル)にヤブキの長さ(約1メートル)をたした長さの櫂の名前です。 |
|
|
|
| |
| ● 櫓(ろ) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
櫓は8の字を書くようにこぐんだ。
こぎ方を身につけるには3ヶ月はかかるなぁ。 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| |
| |
 |
櫓(ろ)は奈良時代(ならじだい)に中国から伝わったものと言われています。
櫓には「トモ櫓<約(やく)5.5メートル>」、「ワキ櫓<約(やく)5.2メートル>」、「マエ櫓<約(やく)4.9メートル>」などがあり、ベカ舟で使う短い櫓は「ベカロ」と呼ばれていました。 |
|
| |