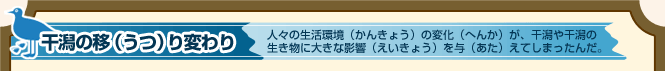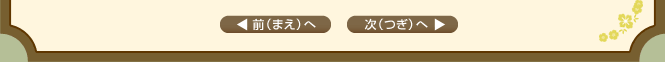|
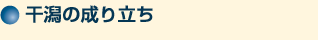 |
 |
| ●東京湾(とうきょうわん)に残る干潟「三番瀬(さんばんせ)」 |
| |
干潟とは、川から流れ出た砂や泥(どろ)が高く積(つ)み重なり、広く真っ平らな砂泥地(さでいち)ができ、干潮時(かんちょうじ)に海面上に姿(すがた)を現したものいいます。毎日2回、潮が引くと空気と太陽にさらされ、潮が満(み)ちると海水でおおいつくされることをくり返します。このような干潟には、たくさんの種類(しゅるい)の動・植物がいます。また干潟は、海の水をきれいにする大きなフィルターの役割を果(は)たしています。
現在では、東京(とうきょう)と千葉(ちば)の県境(けんざかい)の河口のすぐ沖(おき)に、広さ約(やく)1,200ヘクタールの東京湾最大(とうきょうわんさいだい)の干潟「三番瀬」があり、人々に大変親しまれています。 |
| |
 |
 |
 |
 |
干潟はオレたちの海をきれいにしてくれるほかに、たくさんの自然の恵(めぐ)みをあたえてくれたんだ。
今ある干潟は、埋(う)め立てとかしちゃって本来の姿じゃなく、ちがうものなんだ。けれどもオレたちとってはなくてはならないものなんだ。 |
 |
 |
 |
 |
|
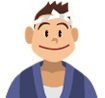 |
|
| |
|
 |