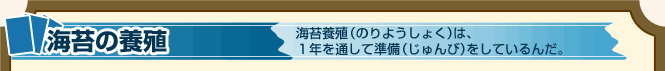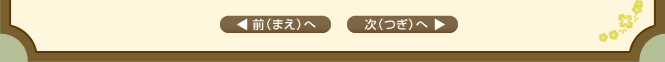|
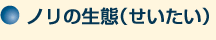 |
 |
| ● ノリの暮(く)らしを解明(かいめい) |
| |
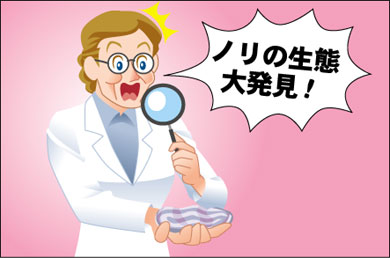 |
| |
 |
 |
 |
 |
この人のおかげでおれたちの海苔養殖(のりようしょく)は、大きく進歩(しんぽ)したんだ! |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
冬の海には、まっ黒いノリが見られます。さて、このノリは春から夏の間、どのように生活していたのでしょうか。昭和(しょうわ)24年(1949)までは、世界中のだれもがわかりませんでした。
この謎(なぞ)を明らかにしたのは、イギリスの女性海藻学者(じょせいかいそうがくしゃ)キャサリン・メアリー・ドリューです。
春になると、ノリの葉からでてきた果胞子(かほうし)〈種(たね)のようなもの〉が貝がらなどにくっついて貝がらの表面(ひょうめん)に入りこみ、貝がらの中で成長(せいちょう)して夏をこすことを発見(はっけん)したのです。
このことが発見されるまでは、漁師(りょうし)は夏が過(す)ぎると海中にヒビを立てて自然(しぜん)にノリがつくのを待っていたのです。しかし、この発見により、自然にまかせていた海苔養殖に、人の手でカキの貝がらを使い種付(たねつ)けをする作業(さぎょう)が加(くわ)わりました。この種付けにより、海苔の生産(せいさん)が安定しました。 |
| |
|
 |