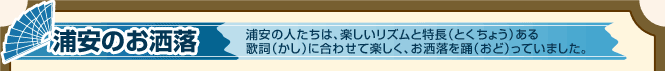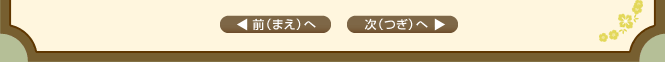|
 |
 |
 |
 |
 |
お洒落は、江戸時代(えどじだい)の終わりから、明治(めいじ)、大正(たいしょう)時代にかけて関東一円(かんとういちえん)に広がった踊りなんだ。
だからよぅ、地域(ちいき)によっては名前が違(ちが)って、「小念仏(こねんぶつ)」「中山踊り」「万作踊り」ってな風にも呼(よ)ばれてたんだ。 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| |
| ●お洒落のはじまり |
 |
 |
 |
 |
 |
空也上人(くうやしょうにん)や一遍上人(いっぺんしょうにん)が伝(つた)えた念仏(ねんぶつ)は、各地域(かくちいき)で形を変(か)え、その地域ならではの踊(おど)りになっていったんだ。 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
お洒落のはじまりは、念仏を唱(とな)えながら鉦(かね)や鼓(つつみ)、笛(ふえ)などのリズムにあわせて踊る「念仏踊り」だとされています。
念仏踊りは平安時代中期(へいあんじだいちゅうき)、空也上人(くうやしょうにん)というお坊(ぼう)さんの「鉢叩(はちたた)き念仏」が元(もと)とされ、その後鎌倉時代(かまくらじだい)に一遍上人(いっぺんしょうにん)が念仏踊りを多くの人たちに伝えました。 |