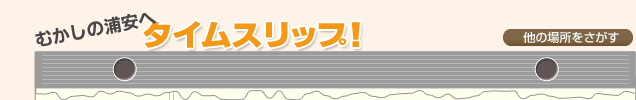
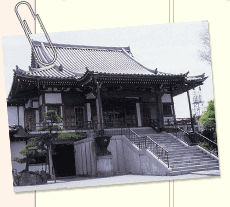
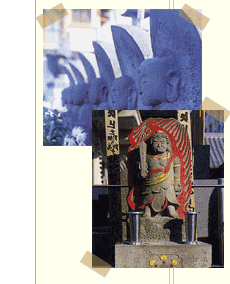
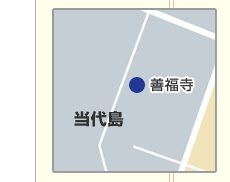
|
 |
|||||||||
| ●かるめや不動尊(ふどうそん)を調査(ちょうさ) 明治(めいじ)から大正(たいしょう)にかけて活躍(かつやく)した「本田 宗久(ほんだそうきゅう)という修験者(しゅげんじゃ)をまつったものです。宗久は病気直(びょうきなお)しの加持祈祷(かじきとう)をしながらかるめ焼(や)きを売り歩いていたため「かるめさん」と呼(よ)ばれ、親しまれていたと言われていますよ。 ※「修験者」とは:修験道を修行する人で、小さな布(ぬの)をかぶり、仏具や衣類(いるい)、食器(しょっき)などが入った足つきの箱を負い、金剛杖(こんごうじょう)を持ち、ほらなどを鳴らして山などを歩いて修行することです。 【調査する内容】 ・「かるめさん」について調べよう。 |
||||||||||
| ●六地蔵(ろくじぞう)を調査 六地蔵(ろくじぞう)は、昭和(しょうわ)5年(1930)にノリ漁(りょう)の準備(じゅんび)で海に出かけた7人の漁師(りょうし)のうち、遭難(そうなん)した6人の冥福(めいふく)を祈(いの)るために、生き残(のこ)ったひとりが建(た)てたんですよ。 【調査する内容】 ・六地蔵以外(いがい)に、善福寺(ぜんぷくじ)にあるものについて色いろ調べてみよう。 |
||||||||||
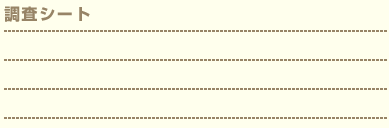 |
||||||||||
